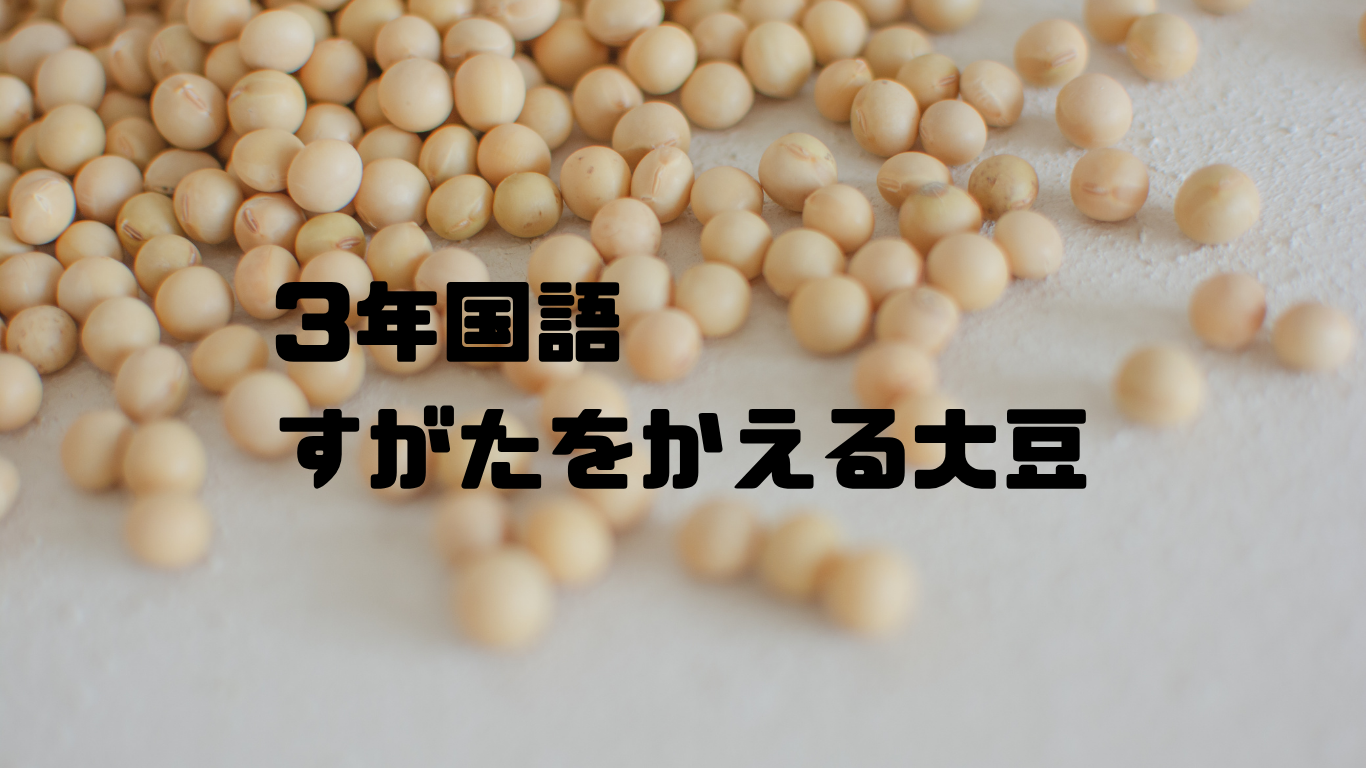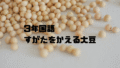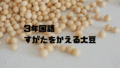「すがたをかえる大豆」の1時間目実践記録です。
一人一人に読みの目的意識を持たせることが一番のねらいです。
まずは題名を読むところからスタートしました。
黒板には「すがた」だけ板書。
「すがたって何かな?」と問いかけると、
「見た目?」「自分の形?」と、子どもたちからいろいろな声が返ってきました。
「すがたを」と続きを書こうとした瞬間、ある子が元気よく「すがたを現す!」。
そのひと言から、ちょっと授業が脱線し、私がドアの陰から“ばあっ!”と出てみせる流れに。
こういう小さなハプニングが、子どもたちとの距離をぐっと縮めてくれるんですよね。
続いて「すがたをかえる」と書くと、今度は男子が「へーんしん!」と見事なパフォーマンス。
女子はくるくる回って変身するよね〜なんて冗談を交えつつ、
「つまり“すがたをかえる”って、変身するということなんだね」と押さえました。
そして今回、国語で変身するのは——
「すがたをかえる大豆」。
板書すると、またあちこちから声が上がります。
「とうふも大豆だよ!」
「枝豆も大豆って、理科で聞いた!」
子どもたちの知識が自然につながっていく瞬間は、本当にいいものです。
いよいよ教科書へ
ここでようやく教科書を開き、まずは範読。
段落番号をふりながら聞かせました。
全8段落——ここが今日の大事なポイント。(大豆だけに、ミソです…)
段落確認をしてから、あえて教科書を閉じるように指示。
普段は「国語は記憶力じゃないよ、文章を読んで考えるんだよ」と言っているのに、今日は真逆の指導。
子どもたちの表情も「えっ、どういうこと?」とワクワクモード。
「さて、大豆は何種類に変身していたかな?」と問いかけると、
「3!」「5!」「7!」とさまざま。
そこで正解を伝えます。
全部で9種類。
みんなで思い出しながら挙げると——
①炒り豆(豆まきの豆)
②煮豆(黒豆・白豆など)
③きなこ
④とうふ
⑤納豆
⑥みそ
⑦しょうゆ
⑧枝豆
⑨もやし
しっかり出そろいました。
しかし、ここで大問題発生!
確認が終わったところで、私は少し演技を入れながら
「……あれ?おかしいぞ?」と声をひそめます。
「9種類もあるのに、段落は8個しかない!!」
子どもたち、ざわざわ。
教科書は閉じたままなので、そりゃあ気になって仕方がありません。
するとある子が鋭い指摘。
「先生、まとめの段落って“もやし”の説明じゃないよね?」
「たしかに…!」
周りも一気に反応し、ここから文章構造の話へ。
説明文のつくりを思い出す
「説明文の構造ってどうなってたっけ?」と聞くと、
「はじめ!なか!おわり!」と、よく覚えていました。
段落と内容の関係を確認しつつ、
「じゃあ、本当に段落がおかしいのか確かめよう」と、最後に教科書を解禁。
子どもたちの集中力が一気に高まります。
段落と“変身”の対応を整理すると…
3段落 …… ①炒り豆 ②煮豆
4段落 …… ③きなこ
5段落 …… ④とうふ
6段落 …… ⑤納豆 ⑥みそ ⑦しょうゆ
7段落 …… ⑧枝豆 ⑨もやし
「なんで??」
「同じ段落なのに、1種類のときも3種類のときもある!」
「なんでまとまり方が違うの?」
子どもたちは完全に“謎解きモード”に突入。
チャイムが鳴って、今日はここまで
続きは明日。
いよいよ、この“段落の謎”に迫ります。
こういう「なんで?」から始まる国語の授業、本当に楽しいです。
明日も楽しみ!
この単元の読み取りの考え方については、
第2時の授業実践で詳しく整理しています。
▶︎(第2時の記事リンク)